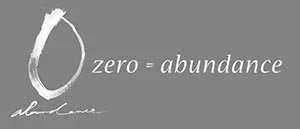私は米国に住んで、環境関連の仕事をしていますが、日常生活および仕事で「CSR」という言葉を目にすることは、ほとんどありません。IR (Investor Relations) などと同じく、企業のウェブサイトの右上に載っているメニューの一つという印象で、その分野に従事している専門家でなければ接する機会もないので、一般の人にとっては、「何それ食べれるの?」という感じではないでしょうか。また、「CSRかCSVか」というような論議も、あまり耳にしないと思います。
英語では、それらはすべて、広義の「Sustainability」という概念の下に来る、やや狭義の考え方になると考えられます。では、「Sustainability」とは何か。日本語では「持続可能性」と訳されてきました。ですが、CSRにしてもCSVにしても持続可能性にしても、ぱっと聞いただけでは固くてぬくもりのない、日本人の琴線には響かない言葉ではないでしょうか。そのせいかどうか、最近は、訳さずに「サステナビリティ」という言葉が使われることが多くなっていると思いますが、本当は「サスティナビリィ」です。アクセントは「ティ」のところにあります。
時折日本のメディアに寄稿させていただくときに、原稿を「サスティナビリティ」と書くと、必ず「ィ」を削除されます。でも、このたかが「ィ」に、日本のCSRにまつわる、意外に根本的な事実が隠れているように感じます。
音楽をやっている方なら、「サステイナー」をご存じでしょう。ピアノのペダルのように、弾かれた音が次第に消えてしまうのを防ぎ、ずっと鳴り続けるように楽器につける装置です。つまり、サスティナビリティとは、ともすれば霧散消失してしまうかもしれないものを、末永く続けられるようにする、ということです。ですから、何も環境や地球のことだけけではありません。夫婦関係であれ、会社の永続性であれ、投資であれ、「末永くうまくいきました、めでたしめでたし」という結末が求められる関係性には、あまねく使える言葉です。
であれば、「サスティナビリティ」と言った時には、環境を守るために滅私奉公します、ということではなく、環境にも配慮しつつ、うちの企業も永続していきますよ、お客さんとのいい関係も続けていきますよ、ということでよいのだと思います。日本語の「三方よし」に当たる、という意見があるのは至極当然です。そして実際、アメリカでいえば、パタゴニア、ベン・アンド・ジェリーズ、メソッドのように、サスティナブルな商品開発をすることが企業の存在理由そのものであり、それが熱狂的なファンの獲得につながり、財政的にも安定・成長している、という企業が続々と出てきています。
おそらくは企業と消費者グループとの対立が珍しくない、欧州の商習慣から発生したであろう「CSR(企業の社会的責任)」は、どちらかといえば世間からのプレッシャーによって生まれたものです。「〇〇をやっていないのは怠慢・無責任だ!」と批判されたから、その声に応えるためにやる、という構造です。仕方がないからいやいややっていた企業も多いのかもしれません。それが90年代~00年代ぐらいでした。
しかし世の中はそれからすでに変わっています。何よりも変わったのは、我々を取り巻く環境です。「地球を守る」などという悠長なことを言っている場合ではなく、加速度的に強度を増す自然災害ひとつをとっても、もはや「人間を守る」という段階に入ってきていると感じます。(この9月にカリブ海をおそったハリケーン・イルマの最大瞬間風速は、80キロともいわれています。次は90キロ?100キロ?)食料資源の逼迫も大きな問題です。食べ物の値段がどんどん高くなっているのは、偶然でも企業の怠慢でも政治のせいでもありません。単純に人口と中産階級の世界的な増加に食料の増産が追い付かないどころか、天候不順による減産のリスクさえもあるのです。
そのような時代ですから、2017年の現在、「サスティナビリティ」は「地球を守る」のではなく、「自分たちを守る」ことになってきているはずです。今までのやり方を踏襲していたのでは、これだけのリスクに囲まれながら、自分たちを守ることはできません。新しい時代の脅威に対応できる、柔軟かつ躍進的な発想の転換が必要とされるのです。
今までと同じインプットとアウトプットの量を保とうとすれば、コストは上がるが値段を上げることはできない、という悪循環に陥ってしまいます。ではどうするか。少ないインプットでアウトプットの価値を上げるしかありません。そしてそこに一つの答えはなく、まさにそれぞれの企業がそれぞれの特性を生かして、新しい答えを見つけていく時代に入ったのだと思います。
輸入された狭義の概念・言葉である「CSR」や「サステナビリティ」を、海外の基準にならってやるのではなく、それぞれの企業が、本来の意味での、それぞれの“Sustainability(サスティナビリティ)“を探していく。そしてその中には、日本ならではの特性を生かしたアイディアや技術もたくさん出てくることでしょうし、それは欧州や米国のスタンダードとは違った新しいひらめきを世界に与えることになる、と確信しています。こうしたサスティナビリティは、エネルギー、ゴミ、特定化学物質の排除などにとどまるのではなく、おそらくもっと大きくて自由な、真っ白なキャンパスにそれぞれの絵を描いていくようなことなのではないかと思います。もはや「取り組み」とさえ言えず、企業の存在理由や理念に直接かかわってくる話になるのでしょう。
米国に住んでいて感じるのは、日本は決して環境への取り組み後進国ではないということです。むしろその逆です。あれだけ細分化されたゴミの分別を各家庭で正しく行い、「節電しましょう」といえば、本当にそれを実行できる能力のある国は、世界広しといえども、そうはないはずです。多くのリソースを持っているし、ノウハウも実績もある。「日本では、CSRはまだまだです」などということは、全くないと思います。もしそうだとすれば、それは「CSR」を狭く定義しすぎているからなのではないでしょうか。
拙訳書「ビッグ・ピボット」の著者アンドリュー・ウインストン氏が指摘するように、世界を覆っている気候変動・資源の逼迫の脅威は、「待ったなし」です。実は、「企業の責任とは何か」をじっくりと考えている場合すらもはやなく、「企業はどうしたら存続できるのか」「我々の社会はどうやったら存続できるのか」に集中しなければならないぐらい、のっぴきならない状況であるのかもしれません。
「ビッグ・ピボット」の中に、「地球は人間がいなくなっても何も困ることはない。ただ、とりついたしつこいノミであるかのように払い落とすだけだ」という引用のくだりがあります。その通りだと思います。地球環境が破壊されても、おそらく地球自体は痛くもかゆくもないのです。ただ、破壊後の変化についていけない生物を淘汰するだけです。恐竜は淘汰したけど、人間は淘汰しないで勘弁してくれる、という保障はどこにもないのではないでしょうか?
もはやサスティナビリティは社会的な責任問題としてやる課題ではなく、我々の生き残りのためにやることです。だから「ビッグ・ピボット」が必要なのです。産業革命以降、世界が作り上げた近代経済システムは、「成長」だけを目標として稼働してきたのであって、「生き残り」のために機能したことは一度もなかったのですから。
テンプレート通りのCSRをやる時代は過ぎ、自分たちにとってもっともサスティナブルな方法で企業を存続させていくことを真剣に考える時代になったのだ。そしてそれは、とりもなおさず、迫りくるリスクに対応して勝ち残っていくことである。ウィンストン氏はそう伝えてくれているのではないかと思います。